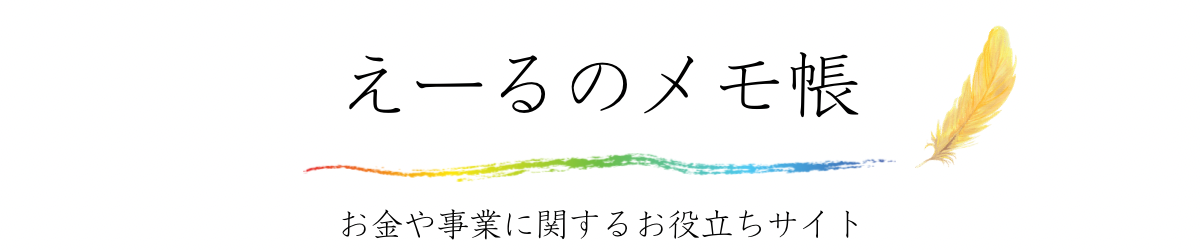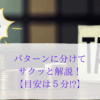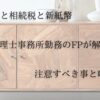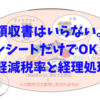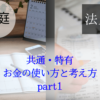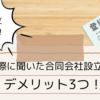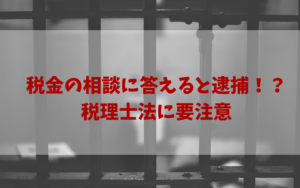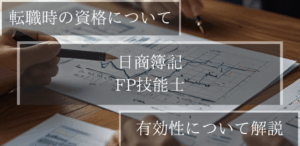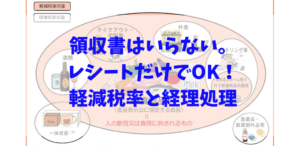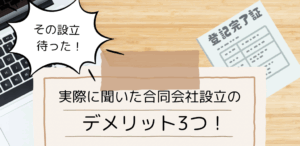現場で見た起業して成功している例と失敗している例【税理士事務所】
起業後に上手くいかなかった例
こちらは順不同で進めさせていただきます。
最後に全部の例に共通するものを書かせていただきます。
起業失敗例①:資金管理のずさんさ

これはこちらで管理するわけにもいかないので最終的には会社側でやっていただくしかないのですが、きちんとした経理担当がついていない会社で起こりがちです。
特に帳簿と現金残が合わない、通帳の残高しか見ていないので税金などの事業以外の支払いに対応できない、などお金がなく慌てるケースが多いです。この場合、個人資金を使ったり、借入でなんとかなったりするのですが、この状態が続くことで段々とお金が回らなくなっていきます。
この現象で不思議なのは、利益が出ているのにお金がないという事です。決算書や試算表では利益が出ているためにお金がなくなるのという考えに至りにくく、問題が発覚するのが遅くなりがちです。
なぜこうなるのかというと、私的な使い込み、会社と個人のお金が混ざってしまう、借入の返済は経費になっていない、などのお金は支払っているのに経費にならない。このギャップが原因です。
きちんと日々、帳簿を付けていく事でかなり問題は改善されるので経理担当を雇うか、税理士に資金繰りの確認と月単位でも帳簿の記帳をお願いするなどで対策してください。

えーる
起業失敗例②:価格設定の失敗

これは最初の単価設定を失敗しまったケースになります。
どの事業にも言える事ですが、最初は顧客獲得の為にサービスをしたり価格を周りより下げて提供する事があると思います。もちろん、そうしないと顧客を獲得できないのも分かります。
ただこの設定があまりにも低すぎたため、赤字を出し続けてしまうというケースがありました。
値上げしようにも応じてもらえない、お客さんが離れてしまう、そうして廃業してしまったり、借入が増え続けてしまったりというパターンです。
これに関してはマーケティングの深い知識はないため対策が難しいのですが、価格以外の品質で差をつけるか、サービスで差をつける、回数券や長期的な契約にする、それこそ立地で優位を取るなど、ある程度の認知度を得た後で顧客が離れられないようにする必要があると思います。
素直に廃業出来れば傷は浅く済むのですが、借入を続けると泥沼化するので気を付けてもらいたい部分になります。
起業失敗例③:現状維持を続ける

これは起業しばらくしてからのお話になるのですが、安定して利益が出るようになりこのままで大丈夫と現状維持を続けるケースになります。
人間は変化を嫌う生き物と言われており、そのままで安定しているのならそれが一番楽だと思います。
ただそのままで安定することはほとんどないです。
よほど新規参入が難しいか、新しい技術に変わることがないものであれば良いのですが、ほとんどは時が経つにつれて売上は減っていきます。
要因は先に挙げた二つの他にも、人口減少や災害、最近であれば新型コロナウイルスによる生活様式の変動など、全く想像のつかない事が起こることもあります。
その中で絶えず変化・成長を続けている企業は生き残っていき、現状維持を続けていた会社は先細りしていく、そんなイメージを持っています。
ただこれは力を入れる方向を間違えると失敗してしまう事もあり難しい問題だと思います。
アドバイスとしては常に情報に気を配り、自分の事業と関連性が深く、初期費用が抑えられるものを見つけるのが良いかもしれません。
起業後失敗例④:過剰投資

これは過剰投資で失敗してしまった例になります。
一言で過剰投資と言っても色々ありますので下で表にしてみました。
①人員
②事業に直接関係のない資産の購入
③事務所の建設
④賃料
他にもあると思いますが、上から順にやっかいな過剰投資について並べています。
詳しくはこれから解説していきます。
起業後失敗例④:過剰投資-1(人員)
まずは人員が過剰になってしまった時ですね。
これは事業者、従業員もどちらも不幸な上に状況を打開するのが難しいです。
本来、従業員というのは会社が必要だと思い募集しているため、従業員側に余程の過失がない場合を除いて解雇するのにはお金が掛かります。明日から来なくていいからで終われるほど甘くはありません。
それに一度会社都合で解雇すると次回のハローワークでの募集が難しくなったり、雇用関係の助成金は一定期間受けられなくなります。
また、その従業員の心情的に会社に良いイメージは持たない事が多いので、口コミなどで評判が落ちるという事も当然考えられます。
そのため一番最初に挙げさせていただいた通り、人員の投資についてはよく考える必要があります。

えーる
起業後失敗例④:過剰投資-2(事業に直接関係のない資産の購入)
こちらは意味が分からないという人もいるかもしれませんが、本当にたまに起こります。
経験としては車が多いのですが、投資用の不動産などを新しく購入したり、株や仮想通貨などの金融資産というケースもあります。
そしてすべてに共通するのが、ローンや借入など手持ちの資金を超えて購入をしているという点です。
さらに売却時にプラマイ0以上に持ってこれれば良いのですが、売却した際にマイナスになるかローンや借入が残ってしまうと最悪です。これは返済の為には資産を売却するしか手がないのに負債だけ残ってしまうという事です。
欲しいものやうまい話に手を出す場合は手持ち資金とよく相談して購入してくださいね。

えーる
起業後失敗例④:過剰投資-3(事務所の建設)
大体は事業が軌道に乗った後に起こるのですが、建設時の借入返済により資金繰りが悪化することが原因になります。
今まで賃貸だった事業者が売上・利益が安定したことで自分で事務所を建てようと思うのはよくある話だと思います。賃借料がもったいないというのが主な理由で、大体は賃借料と返済額が同額に収まるように頭金を考えてもらったり、返済年数を考えてもらったりするのですが、手持ち資金が無かったり、銀行など融資先の返済年数との兼ね合いだったりと、返済額が元々の賃借料を上回ってしまう事があります。
そしてジワジワと資金が減っていったり、返済額が経費にならない事で利益と税金のバランスが崩れ資金不足になったりという事があります。
折角、事務所を建設したのに倒産してしまったり、建設した建物を賃貸に回し自分は賃料を抑えた事務所に移転することになったりと、これも悲しい話になるので資金面には十分に注意して欲しいと思います。
起業後失敗例④:過剰投資-4(賃料)
これは事務所を借りる時や店舗の出店時の賃料が高すぎた場合の話になります。
成功例の①でも出てきた様に、場所確保のためには多少の無茶が必要なケースもあるので難しい判断になりますが、自己資金と回収までの目途をどれだけ正確に計算・シミュレーションできるかで成功と失敗が分かれます。
計算やシミュレーションが難しい場合は1年間の資金や追加資金の確保など、余力を出来る限り作った状態で始めるようにしてください。
賃料が高額になりがちな起業に関しては難易度が上がりますので失敗する例をたまに見ます。
ただこれは運の要素も絡みますので、他の3つに比べて少し仕方ない面もあるので最後に持ってきました。
起業例失敗例まとめ
①は必須項目、②と④は戦略的なお話し、③は戦略・心理的なお話しになります。
①は起業する以上は絶対だと心得てください。
自分でするか経理担当を雇うかはお任せしますが、ここを疎かにして成功は困難でしょう。
②ここは原価・人件費以外にも税金や家賃や営業以外に掛かる経費などにも着目してください。
どれか抜けると後々厳しいという状況になってしまいます。
③は人間の心理による影響もあるのですが、周りが変化する以上は現状維持というのは成り立たないと思ってください。実際に材料や人件費は高騰していないで?その状況で売り上げだけ現状維持というのはありえないと思いませんか?単価を上げると競合会社とのバランスが崩れたりして売上が落ちたりするのです。だからこそ、色々なチャンスを逃さないようにしてもらいたいのです。
④は他の失敗とは違い、紙一重な部分があるので単純に失敗だけでかたずけられないと思います。
一か八かを狙うのかスモールビジネスから始めるのか、時間とリスクを天秤にかけて考えてみてください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
どの項目にも該当するのは勢いだけで進めるのは非常に危険という事です。
そして出来る限り調べる・計画を練る。
資金面に余裕がある方は専門家の力を頼ると成功率は上がっていくと思います。
ここで勘違いしないで頂きたいのは、時間を掛ければいいという訳ではなく掛ける時間は短く、精度は高くを目指してください。個人的には精度よりも速度を優先したほうが成果は生まれやすいと思います。このあたりのバランスは難しいので自分が納得できるものを作ってください。
以上になります。
どこまで力になれるか分かりませんが、ご相談はココナラやXなどのアカウントやブログのお問い合わせからご連絡ください。
ちなみに内容によってはココナラの方は設定の金額より料金をいただくかもしれません。相談についてはある程度無料でお答えするつもりですので、お気軽にどうぞ!
お金の悩みやそれにまつわる疑問や相談お受けします 説得力や信頼性が高まる知識をあなたに。
今回の記事は当ブログの中で最長になりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。